|
|
[腸管出血性大腸菌とは]
大腸菌は、家畜や人の腸内にも存在します。ほとんどのものは無害ですが、このうちいくつかのものは、人に下痢などの消化器症状や合併症を起こすことがあり、病原大腸菌と呼ばれています。病原大腸菌の中には、毒素を産生し、出血を伴う腸炎や溶血性尿毒症症候群(HUS)を起こす腸管出血性大腸菌と呼ばれるものがあります。腸管出血性大腸菌は、菌の成分(「表面抗原」や「べん毛抗原」などと呼ばれています)によりさらにいくつかに分類されています。代表的なものは「腸管出血性大腸菌O157」で、そのほかに「O26」や「O111」などが知られています。大腸菌は、菌の表面にあるO抗原(細胞壁由来)とH抗原(べん毛由来)により細かく分類されています。「O157」とはO抗原 として157番目に発見されたものを持つという意味です(現在約180に分類されています)。
腸管出血性大腸菌は昭和57年(1982年)アメリカオレゴン州とミシガン州でハンバーガーによる集団食中毒事件があり、患者の糞便からO157が原因菌として見つかったのが最初で、その後アメリカだけでなくアルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、オーストラリア、カナダ、スウェーデン、スペイン、チリ、ドイツ、ニュージーランド、フランス、ロシア、中国、南アフリカなど世界各地で見つかっています。
[毒素]
腸管出血性大腸菌は、毒力の強いベロ毒素(志賀毒素群毒素)を出し、溶血性尿毒症症候群(HUS)などの合併症を引き起こすのが特徴です。溶血性尿毒症症候群が発症する機構は十分には解明されていませんが、この毒素が身体の中で様々な障害を起こすことによって、全身性の重篤な症状を出すものと考えられています。
[感染経路]
腸管出血性大腸菌O157の感染事例の原因食品等と特定あるいは推定されたものは、国内では井戸水、牛肉、牛レバー刺し、ハンバーグ、牛角切りステーキ、牛タタキ、ローストビーフ、シカ肉、サラダ、貝割れ大根、キャベツ、メロン、白菜漬け、日本そば、シーフードソースなどです。海外では、ハンバーガー、ローストビーフ、ミートパイ、アルファルファ、レタス、ホウレンソウ、アップルジュースなどです。また、国内で流通している食品の汚染実態を調査したところ、牛肉、内臓肉及び菓子から本菌が見つかったという報告もあります。
[腸管出血性大腸菌による食中毒の発生状況]
発生件数 |
患者数 |
死者数 |
|
平成 8年 |
87 |
10,322 |
8 |
9年 |
25 |
211 |
0 |
10年 |
13 |
88 |
3 |
11年 |
8 |
46 |
0 |
12年 |
16 |
113 |
1 |
13年 |
24 |
378 |
0 |
14年 |
13 |
273 |
9 |
15年 |
12 |
184 |
1 |
16年 |
18 |
70 |
0 |
17年 |
24 |
105 |
0 |
18年 |
24 |
179 |
0 |
本年は既に学校での食中毒による大規模な集団発生が見られているほか、保育施設におけ る集団発生も散見されています。また2006年には、動物とのふれあい体験での感染と推定される事例が報告されており、動物との接触後には充分な手洗いに注意する必要があります。今後も 発生数の多い状況が続くと考えられ、その発生動向には注意が必要です。 食品の取り扱いには十分注意して食中毒の予防を徹底するとともに、手洗いの励行などにより、ヒトからヒトへの二次感染を予防することが大切です。特に、保育施設における集団発生は例年多くみられているので、腸管出血性大腸菌に限らない日ごろからの注意として、特にオムツ交換時の手洗い、園児に対する排便後・食事前の手洗い指導の徹底が重要になります。また、 簡易プールなどの衛生管理にも注意を払う必要があります。
【腸管出血性大腸菌感染症EHEC(O104)】
[経過]
最初に感染がアウトブレイクしたのは5月1日、ドイツからでした。O104大腸菌感染と確認された患者が最後に発症したことが報告されている日は6月26日です。新たに発症する人は、少なくなっていますが、完全におさまったわけではなく、依然として警戒が必要な状況となっています。
これまでドイツ国外でこの細菌による食中毒を起こした人は、いずれもドイツに渡航した人であるか、ドイツに渡航した人と接触した人に限られていましたが、6月の下旬より、ドイツに渡航歴のない患者がフランスとスウェーデンで発生しており、ドイツの流行とは別の感染源があると見られています。
[患者数]
7月7日までに、新しい症例定義の下、EUおよびEEA加盟国内では、これまでに28例の死亡例を含む752例のHUS感染と、16例の死亡例を含む3,016例の非HUS症例が報告されています。
7月6日以降、ドイツ政府は、2名の死亡者を含む8例のHUS感染と42例の非HUS STEC症を報告しました。直近の10日間(6月27日〜7月6日)の間では、9例のEHEC患者と5例のHUS患者が発症しました。確認されたO104STEC患者が最後に発症した日は、2011年6月27日です。全ての症例の中で最後に発症した日は、2011年7月4日でした。
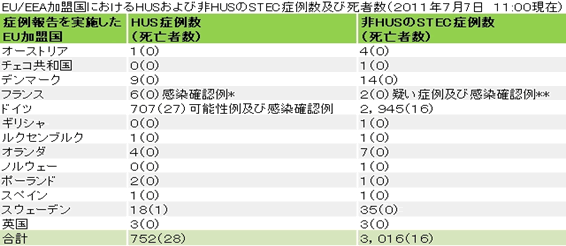
*: ボルドーでのアウトブレイクで新たに報告された症例
**: 以前に報告された症例であって、ドイツへの渡航による疫学的リンクを有する症例
[O104について]
世界保健機関(WHO)は、ドイツ国内で確認された菌について「これまで感染拡大の例がない型」だと警告しました。一方、感染者が多く収容されているドイツ北部のハンブルク・エッペンドルフ大学病院(University Clinic Hamburg-Eppendorf)と提携する中国の北京ゲノム研究所(BGI)は同日、問題となっている病原菌のDNAを解析したところ、「全く新種の強毒性の菌」で、抗生物質に耐性を持つことが分かったと発表しています。 また、米カリフォルニア(California)州の製薬会社ライフテクノロジーズ(Life Technologies)も、独自に検査を行った結果、病原菌が「新種の交配株」の可能性が示されたことを明らかにしています。同社によると、問題の菌は腸管凝集性大腸菌(EAEC)と腸管出血性大腸菌(EHEC)が結合したもので、これが死者を出すほどの猛毒性の一因とみられるということです。
[原因になった食物]
ドイツおよびフランスの食中毒の原因は汚染された豆と芽野菜であることがわかりました。これらの豆、芽野菜の中にはコロハ種子(fenugreek)、緑豆(mung beans)、レンズ豆(lentils)、アズキ(adzuki beans)、アルファルファ(alfalfa)、マスタード(mustard)やルッコラ(rocket)などが含まれています。ドイツおよびフランス国内ではこれらの食品を(産地にかかわらず)生のまま食べない事、イギリス政府も、イギリス国内の豆や芽野菜を生のまま食べないように勧告しています。
欧州連合(EU)当局は7月5日、エジプト産のスプラウト(新芽野菜)の種が感染源だったとの見方を強め、同国からの種の輸入を禁止しました。さらに、エジプトの特定の業者を通じて2009〜11年の間に輸入されたすべての種について、検査と廃棄を指示しました。禁輸措置は全EU加盟国を対象に、10月末まで実施するということです。これに先立ち欧州食品安全庁(EFSA)は同日、エジプトから輸入されたスプラウトの種が、フランスとドイツで広がった病原性大腸菌の感染源になった可能性が高いとの結論をまとめました。
種は業者が出荷する以前に菌に感染していた公算が大きいとし、生産または流通の過程で糞便に汚染されたとの見方を示しましたが、どこで感染したかは依然として不明だということです。
ヨーロッパでのこのアウトブレイクは日本ではあまり報道されませんでした。日本ではEUから輸入される食物は余りないのでしょうね、放射性物質のほうが大問題でした。今までには無かった新種の菌、というのがちょっと不気味です。
ほぼ同じころに日本で起こったユッケに含まれた腸管出血性大腸菌はO111でした。これはHUSを起こす頻度が高い、と前から分かっている菌です。生肉は食べるべきではないのでしょう。
1996年に大阪府堺市の小学校給食で集団発生した腸管出血性大腸菌O157事件では、かいわれ大根が疑われました。、○○農園が使用したかいわれ大根の種子からDNAの同じO157菌が見つかり、一旦は厚生労働省は○○農園のかいわれ大根が原因としましたが、裁判では食材のかいわれ大根及び、○○農園からO157菌が発見されなかったためにかいわれ大根犯人説は否定されてしまいました。状況証拠とアメリカでの新芽野菜によるO157食中毒事例を考慮して、出荷停止や回収命令を出しておけば、その後の数件の事件も防ぐ事ができ、風評被害も抑えられたのではないかと考えます。同日、老人ホームに出荷された同じ○○農園のかいわれ大根でO157事件が発生し、DNAパターンも小学校給食の事件と一致しました。裁判は「疑わしきは罰せず」で決定的な食材からの菌の検出が必要なのでしょうが、公衆衛生上は「疑わしきは速やかに止める」ことです。
今回のEUの例でも、原因がかいわれ大根と同じような新芽野菜(スプラウト)の種との事で、こういった生で食べる野菜には気をつける必要がありますね。日本の「かいわれ大根」が心配となりますが、1996年月に「かいわれ大根生産衛生管理マニュアル」、2003年に「生鮮野菜衛生管理ガイド」がまとめられました。これはHACCP【HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point-日本語読みは決まっていないがハサップまたはハセップと呼ばれることが多い)は 食品を製造する際に工程上の危害を起こす要因(ハザード;Hazard)を分析しそれを最も効率よく管理できる部分(CCP;必須管理点)を連続的に管理して安全を確保する管理手法】の考え方を取り入れたものです。この「生鮮野菜衛生管理ガイド」を守っている業者は安全と判断できますので、納品業者に尋ねてください。