|
|
ここのところ自閉症関連の話が続いています。スペクトラムという単語は本来、1つの現象の中に幾つかの要素が含まれるということです。「連続体」と解釈するのが正しいようです。教育、福祉、雇用、医療などの側面から、「あるべき援助のタイプ」を考えるとき、自閉症か、アスペルガー症候群かあるいは高機能自閉症か、「他に分類されない広汎性発達障害」かというサブカテゴリー診断にこだわるよりも、「自閉症スペクトラム」として捉え自閉症に準じた援助を行うのが有効なようです。
〔概念〕 自閉症スペクトラムとはカナーの提唱した自閉症に、アスペルガーの提唱したアスペルガー症候群、さらにその周辺にあるどちらの定義も厳密には満たさない一群を加えた比較的広い概念であって、社会性・コミュニケーション・想像力の3領域に障害があることで定義されます。典型的な自閉症からアスペルガー症候群、十度の知的障害を伴う例から知的な遅れが無い例まで、連続した一続きのものとみなします。幼児期にはカナータイプの行動特徴を示しても、年齢が長ずるとアスペルガータイプに近くなる子供も多くいますので、これはスペクトラム概念では当然のことといえます。
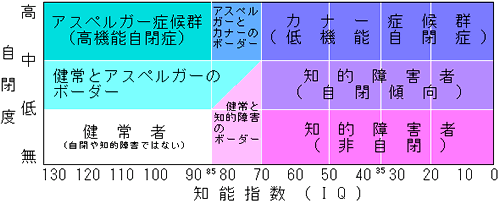
〔診断〕 高機能であるかないかよりも、自閉症スペクトラムであるかないかの診断のほうが臨床的には重要です。IQ70以上というのも、便宜的な基準であって、IQが境界領域の場合に高機能か非高機能かを論じるのは意味はありません。高機能ケースの問題点は高機能であるがゆえに本来必要な社会的援助を得られない、さらに正しい診断を受けることが困難であるということの2点が大きいです。診断は現在の行動を観察すること、これまでの生育暦、発達暦を聞くことから行われますので、専門家でなければ適正な診断は短時間では下せないでしょう。
今は教育の現場でも、ADHD、LD、自閉症スペクトラム児に対する教育のガイドラインが出来てきています。一昔前なら、しつけの問題とみなされていたものが、教師の間でも広く啓蒙されてきています。まだまだ多くの人に理解されるところまでには至っていません。100人に1人、というより、もう少し多いような印象もあります。問題になるのは集団生活を始める時、教育を受ける時なのでしょうから、少しでも多くの人に理解してもらえれば、と思っています。
|
|