
山内 知
(やまうち さとし)
医学博士
日本内科学会認定内科医
日本循環器学会循環器専門医
- 1949年1月
- 京都に生まれる
- 1975年
- 関西医科大学卒業
- 1975年
- 関西医科大学第2内科(循環器)
- 1978年
- 関西医科大学病院CCU
- 1982年
- 関西医科大学洛西ニュータウン病院 内科医長
- 1996年4月より
- 山内医院
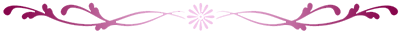
診療案内
内科・循環器科
内科・循環器科は、生活習慣病の治療をメインに、大きな病気にかからないようにすることです。
もし命に関わるような病気になられたときは、速やかに適切な病院を紹介するようにこころがけています。
開業医と病院は役割が違うことを念頭に、患者さんが元気で長生きしていただけることを願っています。
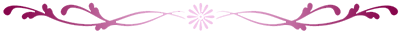
診療方針
循環器病における開業医の役割 『生活習慣病の克服で、元気で長生き』
心筋梗塞や狭心症、脳卒中を予防する治療
ようこそ山内医院のホームページへ。
私は循環器内科医ですが、いわゆる町医者のなかで循環器専門医が果たすべき役割についてひとこと。
消化器関係の病気は、診断や治療において病院と開業医の間に大きな隔たりはありません。胃カメラなどは病院でも開業医でもできます。
しかし循環器領域では、病院でしか出来ない検査や治療がたくさんあります。
心筋梗塞や脳卒中になれば、とても開業医には治療できません。冠動脈血管造影などの大がかりな検査も病院の仕事です。
では、開業医が循環器系の病気で何を診るのでしょうか。
やはり日本人でもっとも多い病気である高血圧と、コレステロールや中性脂肪の値が高くなる高脂血症、またこれら2つの病気に合併しやすい糖尿病だろうと思います。
そして、高血圧・高脂血症・糖尿病の治療を的確に行えば、心筋梗塞や狭心症そして脳卒中は予防できます。
開業医は生活習慣病の治療から始まる
私達いわゆる町医者の循環器専門医は、生活習慣病(生活習慣に関連した病気)と呼ばれているこれらの病気の治療を行い、できるだけ大きな病気にかからないようにするとともに、患者さんが命に関わるような病気になられたときは、速やかに適切な病院への紹介をこころがけます。
患者さんのほうも、病院と開業医の使い分けをじょうずにされて、ただ長生きするのではなく、元気に長生きして、寿命をまっとうされるように心がけられることが大切かと思います。
もう少し詳しいお話は下記の「上手な医者のかかりかた」「診療の萎縮について」をお読み下さい。このホームページからリンクしています。ぜひお立ち寄り下さい。
「生活習慣病について」は東大藤田教授の講演要旨を私がまとめたものが京都医報に掲載されました。一度読んでみて下さい。
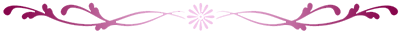
開業医Column
上手な医者のかかり方 『診察の際に、できる限りのことを医師に伝えて下さい』
C型、B型肝炎やエイズが目的の検査は必ず伝えて下さい
まずは医療機関を受診されるときにご注意いただきたいことをいくつかお話しいたします。
当然、受診された理由があるわけですし、それは診てもらう先生にお話しされるでしょうが、C型肝炎やB型肝炎、そしてエイズなどの検査を目的に来院されたときは、必ずそのことを医師に伝えて下さい(ただし、法的には健康診断目的は保険診療の対象外です)。
手術前の検査や、胃カメラ等の観血的操作が予想される検査においては、これらの検査は保険診療上傷病名なしで認められておりますので、このような検査をされる前の血液検査では普通C型ならびにB型肝炎の検査とエイズの検査は実施しますが、一般的な採血では実施しないこともあります。あまり血液検査を受けられないような人は特にC型肝炎に関しては、一度検査して陰性かどうか確かめておかれた方が良いかと思います。
また、現在C型肝炎に罹っておられる患者さんに関しましては、保険診療上、インターフェロンの長期投与が2002年の2月から認められるようになりましたので、最近C型肝炎の治療方針が変わっています。
献血者に占めるエイズ陽性は日本が最も高い率
以前インターフェロンの適応外と言われた患者さんでも、もう一度受診して治療方法を相談された方が良いと思います。
また、エイズも若い世代を中心に、特に東京近郊や大阪など大都会で増加しております。
この頃ではエイズの治療方法も進歩してきていますので、もちろん予防が第一ですが、早期発見早期治療も大切です。
日赤の献血ではこれらの検査は実施して、患者さんにその結果を通知しておりますが、先進諸国の中で献血者に占めるエイズ検査陽性の比率は日本が最も高い率となっています。
実数はそんなに多くはないのに、比率としては高い値となっているのは、検査目的で献血をしている数が多いからだと思われます。
保健所でも検査は実施されています。
他の病院や診療所での治療も事実を伝えて下さい
その他に必ず医師に伝えていただきたいことがいくつかあります。
まず、現在ほかの病院や診療所などで治療を受けておられる方は、その病名と治療内容を知らせて欲しいのです。内服薬があるならその内容を、注射を定期的にしているならその事実を教えて欲しいのです。
以前のようにビタミン注射を受けている人は少なくなってきていますから、定期的に静脈注射をしている患者さんといえば、B型肝炎とC型肝炎が多いかと思います。
これらの病気に使用する静脈注射は大部分がノイファーゲン製剤といいまして若干血圧を上昇させる傾向がありますから、我々は定期的に静脈注射を受けていると聞かされれば、血圧に要注意と考えるわけです。
投薬されている内服薬に関しては、その名前を記載された紙をお持ちなら、必ず持参して医師に見せて下さい。薬剤の内容を書いたデータをお持ちでないなら、薬そのものを持参して見せていただいても結構です。
現在治療を受けている病気と、その治療内容を知ることはその患者さんを診る上で大変参考になりますし、逆に知らせていただかなかった時は、危険なことも起こりかねません。
また、生活習慣病の1つである糖尿病に罹っておられる患者さんでは、糖尿病性網膜症は早期発見早期治療で失明を防げますので、当然眼科も併せて受診しておられることと思いますが、眼科を受診されるときに、最近の血糖値やHbA1Cの数値も眼科医に知らせて下さい。
ちなみに成人の失明を来す最大の原因は糖尿病性網膜症です。
過去の治療でアレルギーが出た方も必ず伝えて下さい
つぎに、今までに受けた治療で何らかのアレルギー症状がでたことのある人は、必ず伝えて下さい。
例えばある薬を飲むと蕁麻疹がでるとか、検査の時に造影剤の注射をしたら苦しくなったとか、あるいは、アレルギーではありませんが、風邪薬を飲むと眠気が非常に強く出るといったことも、個人差が強いために参考になります。
例えば、高血圧で長期にわたって降圧剤を投与されている患者さんが、あるAという抗生物質にアレルギーがあったとしましょう。
最初に診察を受けたときに医師にその旨を伝えていても、こちらも聞いていながら、うっかり忘れて投与することもあり得ますので、こういう患者さんは「抗生物質を出します」といわれたら必ず、Aという薬にはアレルギーがある旨を、しつこいと言われようとも再度言って下さい。
虫垂炎や帝王切開でも、手術や入院をした場合は全て伝えて下さい
続いて、伝えて欲しいのは、いままでに罹った病気です。
手術した病気や入院を必要とした病気は全て教えて下さい。
それと大切なのは輸血を受けられたかどうかです。輸血を受けた方は必ず言って下さい。また、大きな手術を受けられた患者さんは、血液製剤を投与されている可能性も考えられますのでその旨を伝えて下さい。
虫垂炎の手術や帝王切開は手術と思っていない人が多いようで、「手術は何もありません」と答えられた患者さんに「盲腸炎の手術は」、「出産は正常分娩でしたか」と尋ねてはじめて答えてくれる人が多いようです。出産時に巨大児を出産しますと、将来母親が糖尿病になる可能性もありますので、出生児の体重があまりに重い子供を出産されたお母さんも、その旨を伝えておいて下さい。
また、全然関係のないと思われる病気も一応言って下さい。1例をあげますとアトピー性皮膚炎の患者さんで目が見えにくくなったといえば、我々はまず網膜剥離を疑います。
家族の方の病気、病気に遺伝子の関与する可能性は高い
次に血縁関係のある家族の方の病気です。若くして死亡した人が多いと聞けば、家族性高脂血症を疑います。糖尿病、高血圧、高脂血症等の生活習慣病は遺伝素因も大きな因子です。癌などの悪性腫瘍も注意すべき疾患といえます。
最近EBM(evidence based medicine)といって多数の症例に対して行った治療の中で、最も適した治療方法を推奨するという治療方法が主流を占めていますが、今後遺伝子解析が進めば、EBMからtailor-made medicineすなわち、個々の症例に最適な治療へ移行することも予想されます。簡単に言えば、80%の人にはこの降圧剤を勧めますが、あなたにはこちらの方がいいかもしれません。といったことも遺伝子解析が進めば可能になる状況が、そう遠くない時期に到来しそうです。
いまは、まだそこまでは進んでいませんが、各種の病気に遺伝子の関与する可能性は高いので、血縁関係の人の病歴は参考になります。将来遺伝子の研究が進めば、それぞれの患者さんの血液をとって調べて、傷ついた遺伝子を探し出し、それを修復するか、あるいは予想される癌などの、ワクチンを接種して発症を予防するといった治療も、夢ではなさそうです。
少し脱線しますが、そうなりますと人間の寿命は120歳と言われておりますので、社会全体に及ぼす影響は相当なものと予想されます。
自宅の循環風呂、温泉後の高熱、海外旅行も疑いはある
その他のことでは、自宅で循環風呂の施設を使用されている方は、レジオネラ菌による感染症を考慮しなくてはなりませんので、これも医師に伝えて下さい。温泉に行ったあとで高熱が出てもやはりレジオネラを考えます。
また、最近海外旅行へ行かれた方は行き先を伝えて下さい。旅行先で流行している病気は、インターネットで国立感染症情報センターにつなげばすぐに判る時代です。
特にマラリアは医師も経験不足ですが、検査技師も経験不足ですので、血液標本を顕微鏡で見るときに見落とすことがあるそうです。したがって血液を、一般の診療所のように院外の検査施設へ検査依頼するときには、検査用紙にマラリアの疑いもある旨を記載して、見逃されることのないように注意するように私どもは教えられておりますので、マラリア流行地からの帰国のときには必ず医師に伝えて下さい。
診療の萎縮について 『検査と治療の萎縮は医療機関が抱える大きな問題』
様々な検査を実施していた診療からの萎縮傾向
最近少し気になる「診療の萎縮」についてお話しします。
20年くらい前は、一度の採血で多数の項目を検査しても、保険診療として認められていましたし、多項目を検査したからといって診療機関が赤字になることはありませんでした。検査漬けの医療費無駄使いと批判された所以ですが、その時代は初診の患者さんなら、現在もなされているような一般的な検査項目以外に、リウマチの検査、甲状腺機能、いろんな腫瘍マーカー、各種肝炎ウイルス、電解質、梅毒の検査などいろんな検査をして、何か網にかからないかという、いわば邪道ともいうべきことが行われていました。
まず、様々な検査をして結果が出てから考えるという医師が多かったと思います。
そのような時代にあっても、医療費抑制と医療の本来の姿を考えて、必要と思われる検査のみをするように指導していた大学医局もあったそうですが、大多数の診療機関はこのような、網を広げて何かが引っかからないかという考え方でした。患者さんの側にもまた、医療機関に診療報酬を支払う保険者側にも有り余るお金があれば、この方式は決して間違いとは思いませんが、最近のように患者さんの負担率が上昇し、また保険者も赤字となってきた現在では以前のようにはいきません。このごろは多数の項目を一度の採血で検査すると、診療機関に赤字が出る仕組みになっています。
また、患者さんの負担率の上昇に伴って、窓口での支払額が多額になるために、診療サイドも出来るだけ少ない項目に押さえようとします。その結果網の目が広がり、逃げていく魚が出てくる可能性も考えられます。これは言い換えれば「検査における診療の萎縮」ともとれる事柄であります。
薬漬けと呼ばれていた薬の処方に対しての是正
また、薬の処方でも同じようなことがあります。数の計算方法は複雑なのですが、多数の薬を投薬すると、院内処方の場合は診療機関の赤字となる仕組みになっています。
また、院外処方では赤字にはなりませんが処方箋料が減額されます。前述の検査漬けに対して、こちらは薬漬けと呼ばれていた医療に対して、これを是正しようとする試みです。
薬価差益と呼ばれておりますが、昔は薬を出せば出すほど収入が増加する仕組みになっていました。そのために一部において必要以上の投薬がなされていた事は否定しません。
しかしながら、最近ではこの薬価差益はほとんどなく、院内処方の診療機関では在庫薬品との関係で、むしろ薬品部門は赤字状態のところが多いと思います。ところが一方で、本当に多数の薬剤が必要な患者さんもおられるわけです。比較的重症の糖尿病に高脂血症と高血圧を合併し、心筋梗塞や脳梗塞の既往などがあれば、相当多種類の投薬を余儀なくされることもあります。
院内処方の医療機関はこのようなときに困るわけですが、こういう患者さんだけを院外処方にしている医療機関もあります。また、月に2回以上受診してもらって、1回目の受診時と2回目の受診時に異なった薬を、おのおの1ヶ月分投薬するという方法をとっている医療機関もあります。
あるいは、必要最低限に投薬をおさえている医療機関もあるでしょう。これすなわち「治療における診療の萎縮」であります。
収支の考えのない医療行為はもはや存在しない
アメリカの年間総医療費は約150兆円に対し、日本の総医療費は約30兆円。人口はアメリカが日本の約2倍ということを考慮しても、日本の医療費はそんなに高額とは思いませんが、現在の医療費抑制策によって、このような「診療の萎縮」を招来する可能性を秘めております。
本来医療とは、その患者さんにとって必要なことを、全力で手助けするのがその本質ではありますが、国公立の医療機関でさえその経営状態を問われている今日においては、収支の考え方なしでの医療行為は、もはや存在し得なくなっております。
患者さんの立場に立った医療とのギャップ
それでは、患者さんのサイドからはこの問題に対してどうしたらよいかと尋ねられれば、実は返答に窮します。
検査に関しては、「支払額が少し高額になっても構いませんから、必要な検査はして下さい」と告げられるのも一つの方法かと思います。
投薬に関しては、「どうしても多数の薬剤が必要なら院外処方箋を出して下さい」と伝えられる方法もあるかと思います。
その他にもいろいろな手段はあるかと思いますが、現在の医療機関は上述のような問題を抱えていることを理解していただいた上で、主治医と話し合われることが大切かと思います。
生活習慣病について 『健康で長生きする"Succsesful Aging"を目指した治療』
東京大学大学院医学系研究科
内科学教授 藤田敏郎氏(講演要旨:文責 山内 知)
心筋梗塞の発症率が高いシンドロームXという概念
Metabolic Syndromeという概念が話題になっている。
シンドロームXとも呼ぶが、内臓肥満、中性脂肪高値、低HDL血症、耐糖能異常、高血圧を併せ持つ病態で、インスリン抵抗性の関与が指摘されており、心血管イベントのリスクが高い。PROCAM Studyによれば、心筋梗塞の発症率は、高血圧があると約2倍、糖尿病だけでも約2倍だが、高血圧と糖尿病を両方合併すると8倍になる。
さらに高血圧、糖尿病、高脂血症が合併すると20倍になる。以前は高血圧だけをもつ人が多かったが、ライフスタイルの変化により2000年に出されたFramingham Studyでは、高コレステロール血症、高血圧、低HDL血症、糖尿病の合併が増加している。
食事や運動よりもストレスが高血圧に要因する
高血圧の非薬物療法として、食事療法、運動療法、心療内科的アプローチがある。
特に食事療法が重要で最も重要なのは食塩制限であるが、最近話題になっているのが、K(カリウム)、Ca(カルシウム)、Mg(マグネシウム)である。
また、カロリー制限も重要で高血圧の患者さんの7割が肥満だと欧米では言われているが、肥満高血圧では塩分制限以上にカロリー制限が推奨されている。
運動そのもので体重減少がみられなくても血圧は下がり、脂質代謝、糖質代謝に好影響を与える。
ストレスに関しては高血圧のガイドラインに入っていない。
しかし多くの専門家はストレスが食事や運動に勝るとも劣らない重要な要因と考えている。
KやMgを豊富に摂っている地域では高血圧の頻度が少ない
まず塩分と高血圧との関係であるが、50数年前の秋田県は、1日30gの塩を摂っており、40%が高血圧になり脳出血が多発していた。広島は12~13gで高血圧は20%、アメリカは10gで10%。エスキモーはほとんど塩を摂らず高血圧はいない。すなわち塩分摂取量と高血圧には極めて良い相関がある。
しかしその後、塩分摂取が多くても必ずしも高血圧が多くない地方も見つかってきた。KやMgを豊富に摂っている地域では、塩分摂取が多くても高血圧の頻度が少ない。とはいうものの塩を全く摂らないところでは高血圧はない。現在でもそういう人種は存在し、エスキモー人のみならず、ピグミー族、ケニアの遊牧民、そしてオーストラリアの原住民、ニューギニア高知民族、最も有名なのがブラジルの奥地に住んでいるヤノマモインディアンであり、食塩の摂取量が1日0. 5gというほとんど無塩食である。
塩分摂取を3g以下にすると極めて効果的に血圧が低下し、6g以下でもかなり下がる。ただ、塩分に対する感受性に個人差がある。30名に1週間の減塩食の後、15gの食塩負荷をおこない、再び減塩食を与える。すると半数は、減塩で血圧が下降し塩を負荷すると上がる。そしてラシックスを投与すると下がる。極めて塩に敏感に反応する(食塩感受性高血圧)。残りの15名は減塩でも血圧が下がらないし、また塩を負荷しても上がらない。利尿薬抵抗性である(食塩非感受性高血圧)。減塩が有効なのは食塩感受性であって、非感受性にはあまり効果がない。食塩感受性の人にこそ積極的な減塩を勧めるべきで、将来は遺伝子診断、Tailor Made Medicineへと向かうべきである。非感受性群や健康人では、すみやかに尿の中に塩が排泄される。食塩感受性群では腎機能は正常であり、原因は不明だが塩の排泄が悪い。神経や内分泌因子の関与が疑われる。食塩感受性は遺伝によって受け継がれていくが、腎機能が悪くなれば、Na(ナトリウム)の排泄が低下し食塩感受性になる。加齢によって腎機能は低下するし、糖尿病や高血圧はさらに腎機能を低下させる。高齢者では塩を制限すると血圧が下がるが、Naの保持能力も低下しており極めて安全域が狭く、厳格な減塩は危険である。また、高齢者ではKの保持能も低下している。
塩による血圧上昇をKが抑制した
Kに話を移す。
ヤノマモインディアンは、Naの摂取量はアメリカ人の10分の1であるが、Kの摂取量はアメリカ人の3倍である。木の実やジャガイモなどの野菜を食べているのでKが非常に多い。塩が少ないとともにKが多いということが高血圧を防いでいるのではないかと考えられる。
以前に私どもは、K負荷の試験を行った。まず減塩のあと食塩負荷を1週間行ったところ、食塩感受性高血圧では、収縮期、拡張期とも血圧が上昇する。しかし塩とともにKを投与すると上昇しない。塩による血圧上昇をKが抑制したということになる。
アメリカでは利尿薬が高齢高血圧のスタンダードだった
Kにはナトリウム利尿作用がある。SHIEP試験(1991年)は高齢者の高血圧で最も有名なもので利尿薬が脳卒中を抑制したことから、アメリカでは利尿薬が高齢者の高血圧のゴールデンスタンダードになった。これを裏付けするように、最近JAMAに掲載されたALLHAT試験というのがある。アムロジピン(ノルバスク・アムロジン)もリシノプリル(ロンゲス・ゼストリル等)も効果はあるが、やはり利尿薬が有効ということになった。アメリカでは第7次のガイドラインが出ようとしているが、利尿薬が第1選択になると聞いている。しかしながらクロルタリドン(ハイグロトン)群はアムロジピン、リシノプリル群に比べて低K血症が多く、私は利尿薬は半錠あるいは半錠を1日おきで十分と考えている。ALLHATではKが不足して、その結果糖尿病になるのが32.7%あり、アムロジピンやリシノプリルよりも利尿薬群に多い。ALLHATの期間5年ではイベントには関係なかったが、将来この糖尿病がどのように影響してくるかという危惧はある。
日本人は原始人の食事を見習わなくてはならない
前述のSHIEP試験を10年後に見直すと、利尿薬は確かに脳卒中を減らすが、Kが3.5以下の群では脳卒中が増えている。2群間に血圧の差はなく、血圧以外の因子で脳卒中が起きている。Kには降圧作用があると言ったが、直接の臓器保護作用もあることになる。Kはインスリン抵抗性を改善する。食塩感受性のネズミに塩を負荷すると、酸化ストレスのマーカーが上がってくる。ところがKをやると正常化する。塩には酸化ストレスの作用があり、Kには抗酸化ストレスの作用がある。インスリン抵抗性と食塩感受性、糖尿病と高血圧はリンクしている。高インスリン血症になると、交感神経系が緊張し、食塩感受性が起こり、さらにインスリン抵抗性を起こす。DASH試験によりKが血圧を下げることが証明され、次のガイドラインにはKが入るということを聞いている。日本人はNa/K比が欧米に比べて高い。少し原始人の食事を見習わなければいけないということになる。
文明の進歩で大きく変わったのは食塩とストレス
ストレスが循環器に関係するというのは、多くの循環器の医者が考えていたが、再現性に乏しいことからエビデンスがない。ホワイトカラーの男性はブルーカラーの男性よりも冠動脈疾患が2倍多い。夫に死別した女性は、夫が健在な女性よりも心筋梗塞の発症が2倍多くみられる。自分で測れば正常なのが、医師が測れば上がる白衣高血圧。これは確実にストレスによる高血圧である。イヌは高血圧を作りにくい動物だが、イヌにストレス負荷だけ、あるいは食塩負荷だけを加えても高血圧にはならないが、両者同時に負荷すると慢性的に高血圧を作ることが出来たという報告がある。文明の進歩で大きく変わったのは食塩とストレスと言われているが、両者には相乗効果がある。私どもは、塩に敏感なネズミに対してストレスをかける試験をした。食塩感受性のネズミにストレス負荷をかけると、腎臓の交感神経が興奮し尿中のNa量が減る。正常のネズミにストレスをかけても、腎臓の交感神経活動は興奮しないし尿中のNa量も減らない。食塩感受性であってもKを補給しておくと、ストレスを与えても尿中のNa量、尿量ともに減少しない。Kは塩に打ち勝つとともにストレスにも打ち勝つ。人に対しておこなった試験もある。精神的ストレスということでIQテストを行うと高血圧の人は、腎の交感神経活動が亢進して腎血流が減少する。正常血圧群では2つに分かれて、高血圧の家族歴のない人はまったく平気だが、本人がたとえ正常血圧であっても、高血圧の遺伝子を持っている人では腎血流が低下する。つまりストレスに感受性であり、ストレス感受性というのは遺伝によって起こると言えるわけである。少しまとめてみると、高血圧の発症メカニズムのうえで、ストレスと食塩というこの2大環境因子が大変危険である。ストレスが加わると、腎の交感神経活動が興奮してNaの排泄が低下する。そして塩が加わると、Naの貯留が起こって高血圧になるという考えである。さらにストレスあるいは塩に対する感受性が個人個人で異なり、現在遺伝子研究が行われつつある。
Mgが不足すると細胞内のCaが増加し、血管収縮や不整脈を起こす
産科の子癇の治療にMgが使われるが、Mgについて述べる。動脈に緩序にMgを投与すると血管拡張が起こるが、Caを同時に投与すると血管は拡張しない。血管の平滑筋細胞の細胞膜にCaチャンネルがある。Caが細胞内に流入すると血管が収縮し、流出すると血管拡張が起こる。これをレギュレートするのがCaチャンネルで、またそれをレギュレートしているのがMgである。Mgが不足すると細胞内のCaが増加し、血管収縮や不整脈を起こす。Mgが十分にあると血管拡張が起こる。アメリカではMgのことをNature's Calcium Channel Blockerと呼んでいる。豆腐にMgが多く含まれるが、ぜひMgを摂っていただきたい。Mgは血管拡張薬、天然のCa拮抗薬である。6年前に、Ca拮抗薬服薬者に心筋梗塞が多いという成績が出た。多くの試験が追試されたが、短時間作用型のCa拮抗薬に限った話のようである。ニフェジピン(アダラート等)を投与すると急激に血圧が下がり、反射性の交感神経亢進が起こり、血小板の活性化や血管収縮により心筋梗塞の危険が増す。Caチャンネルには、L型の平滑筋細胞のCaチャンネルとともに、神経にもN型のCaチャンネルがある。ニフェジピンは血管を開くために開発されたので、L型のCaチャンネルに特異的に効く。Ca拮抗薬は血管を拡張するが反射性の交感神経の亢進を起こす。しかしMgをやっておけばN型のCaチャンネルを抑制するので反射性の交感神経緊張を抑制する。Ca拮抗薬はほとんどがL型抑制のみだがシルニジピン(アテレック、シナロング、シスカード)というのはN型も抑制する。朝方に交感神経が緊張し心拍数も血圧も上がってきて、脳卒中が多い。勤労者では月曜日に交感神経が優位になり心筋梗塞が多い。最近では心拍数が動脈硬化の指標といわれている。交感神経の亢進で血圧が上昇、インシュリンも高くなる、コレステロール、TG、ヘマトクリットも上がり、頻脈は動脈硬化の危険因子である。CASTEL試験では高齢者の心拍数が予後を左右する結果が出た。家庭での心拍数が80以上の人では12年間で生存率が低下し、64未満なら予後が良い。Ca拮抗薬は優れた薬だが心拍数上昇に問題がある。N型もブロックする薬剤の使用をお勧めする。
文明人はNaが増え、K、Mgの減少に加えてストレスが増大
非薬物療法も大切で食塩の摂取量を10gに減らし、Kの摂取量を1g増やし、肥満度を24%から18%に、男性の多飲者24%を18%に減少させ、毎日30分の早歩きを国民の10%が行う。これで収縮期血圧が3.8下がり、脳卒中の死亡率は27%、総循環器疾患死亡率は28%減少させることが出来る。 私たち文明人は、以前は塩分が少なく、K、Mgの多い食事を摂っていたが、嗜好の変化とともにNaが増え、K、Mgが減ってきた。それとともにストレスフルな社会が形成されて、精神的ストレスが多くなった。さらには肥満、運動不足、アルコール、タバコといったものが加わって、高血圧が生まれてきた。日本は、世界に類を見ない形で高齢化社会を迎えようとしているが、高血圧によって脳卒中や心筋梗塞になっては困る。それを予防することが大切である。また高血圧になった場合には、降圧薬療法とともに非薬物療法をおこなって、脳卒中、心筋梗塞を抑制する必要がある。ただただ長生きするのではなく、健康で長生きするということが大切で、Succsesful Agingという言葉があるが、ぜひSuccsesful Agingを目指して治療していただきたい。